フロム・ファースト・センテンス 2 issue3
2019.07.08
阿部海太 / 絵描き、絵本描き。 1986年生まれ。 本のインディペンデント・レーベル「Kite」所属。 著書に『みち』(リトルモア 2016年刊)、『みずのこどもたち』(佼成出版社 2017年刊)、『めざめる』(あかね書房 2017年刊)、共著に『はじまりが見える 世界の神話』(創元社 2018年刊)。 本の書き出しだけを読み、そこから見える景色を描く「フロム・ファースト・センテンス2」を連載中。 kaita-abe.com / kitebooks.info
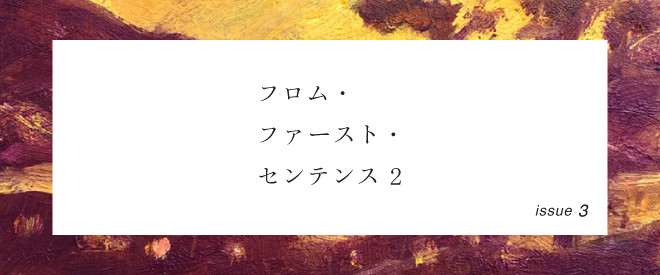
ファースト・センテンス /
「自分が見たすばらしいものを君に報告はしようと、僕は外の世界をちょっとだけ丹念にめぐって来ました。」
手紙のような可愛らしい言葉が並ぶ書き出しである。
生粋の旅人が使う言葉ではないだろう。
どちらかというと“観測者”の言葉というほうがしっくりくる。
帰る場所があり、報告する人が居る。
それはホーボーではなくトラベラーだ。
ここで「ちょっとだけ丹念に」という言葉が気になる。
何だか時間と心の余裕を感じるセリフだ。
僕はこのセリフから、空路でも陸路でもなく航路の旅を想像する。
それほど大きくはない船に乗って、港と港をゆらゆらと繋いでゆく。
そんな前時代的な旅を一度はやってみたいと思うが、
もしかしたらこの物語もそんな古い時代が舞台なのかもしれない。
そう考えると、これらイノセントな言葉選びにも合点がいく。
飛行機もなく、鉄道も普及していない、
まだ世界がとてつもなく大きく未知だった頃の旅とは、
いったいどんなものだったのだろう。
ガルシア・マルケスの『百年の孤独』という途方もなく面白い本がある。
「マコンド」という不思議な村で暮らすある家族の物語で、
雨が“四年十一ヶ月と二日”降り続いたり、
娘がはばたくシーツに包まれながら空高く消え去ったり、
豚のしっぽを持った赤ん坊が生まれて来たりと、
数え切れないほどの神話的シーンが前振りもなく唐突に描かれることから、
「マジックリアリズム」と評される大変稀有な作品だ。
そんな幻想的な本の書き出しには、
「初めて氷というものを見た、あの遠い日の午後を思い出したにちがいない。」
という記述があるのだが、あれだけスケールの大きな物語の冒頭に、
このような素朴なエピソードが据えられた意味を改めて考えてみる。
きっとかつての世界とは、あらゆるものが奇妙で捉え切れないものばかりだったのだ。
太陽の光にきらめく冷たい氷は、降り止まない雨や、空を飛ぶ娘や、
しっぽの生えた赤ん坊と同じくらい不思議なものだったに違いない。
不思議で満たされた世界を、マルケスは科学も神話もまるで同じもののようにあつかい描いた。
ともすれば、これはある時代のある地域についての至極真っ当な「報告」なのかもしれない。
「とぷとぷ」と船縁に穏やかな波がぶつかり、
夕空を映した水面は見たこともない色に輝いている。
湾に面した小さな町からは音ひとつ聞こえてこない。
船上の観測者はしばし人で居ることをやめ、
離れた場所から人の世界を物珍しそうに見つめている。
山や木の形を目でなぞり、灯り始めた家のあかりを数え、
人間の営む世界とはどんなものかと、
まるで異界からの使者になったつもりでひとり思考して遊んでいる。
例えば黄昏のひなびた港町について、そこで暮らす人々について、
人でなき観測者はいったいどのように報告するのだろう。
まるで滑稽だったと言うのだろうか。
それとも美しかったと言うのだろうか。
