「記憶の波」
2014.07.24
ponto…2014年3月、小説家・温又柔と音楽家・小島ケイタニーラブが、朗読×演奏によるパフォーマンスをはじめ言葉と音を交し合いながら共同制作するために結成したユニット。同年9月、構成・音響・演奏をとおして2人の活動を支える伊藤豊も雑談家として加入。 SBBで行われている温又柔と小島ケイタニーラブの創作イベント「mapo de ponto」でできた作品をこちらのページで公開中。
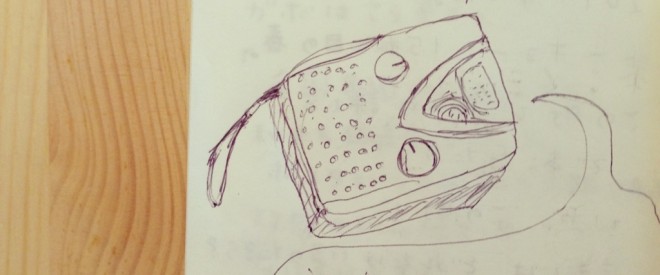
du 2 記憶の波(温又柔)
昨日までの雨がやみ夏の予感がする最高の天気。
それだけで口笛を吹きたくなる一日の始まりだ。
何しろ、本日は“自由の身”。
大きな仕事を終えたばかりなので、有給をとった。
慌ただしく出かける妻を悠然と見送り、2杯目のコーヒーを味わう。
“さて、どんな休日を過ごそうか。”
えらくもったいぶって考えてみる。
仕事場と自宅を寄り道もせず行き来して図版や組版や色の組み合わせとかをいじって直して崩してまた整えてーーという生活を二ヶ月近く過ごしたのである。おかげで自分自身の身なりはないがしろもいいところ。コーヒーカップを洗いながら、髪でも切るか、と思いつく。数年来通っている美容室に電話すると、
<おー、久しぶりですね! 今日ですか? 午前中ならいつでも大歓迎ですよ。お待ちしております。>
こりゃ幸先がいい。
鏡にうつる短髪の自分は、なかなか悪くなかった。正午を迎える日差しが眩しい。今日は暑くなりそうだ。目黒川沿いのカフェでハンバーガーをかぶりつきながら、平日のまっぴるまにぶらぶらするヨロコビも一緒に噛みしめる。
午後になったら、行くところは決めてある。ここから急行でひと駅となりの学芸大学。
美容室に何冊か積んであった雑誌のうち、『POPEYE』を手にしたときだ。
東京特集
こんな特集があちこちの雑誌でくり広げられている季節なのだ、今は、と思う。身に覚えがありすぎてこそばゆい。上京したばかりの頃は、いつもびくびくしながら東京のあちこちに出かけたものだ。いなかもんと思われるのを恐れながらも東京のいいところをめぐりたい好奇心はおさえることができなかったーー。
あの頃のオレからしてみたら、いまのオレなんていいオッサンだろうなーと思う。
何しろ、もう15年も経っている。15年! あと数年もすれば、地元で育った年月よりも東京にいる時間の方が長くなる。
そんなこと思いながら雑誌をめくっていると、何やらよさそうな本屋が目に入る。
名まえは<SUNNY BOY BOOKS>。
そこは、店名のとおり、まさに今日のような天気のいい初夏によく似合うたたずまいの本屋だった。
シャレた風情の店員ーーたぶんまだ20代のーーが、やはり同じ歳ごろの常連らしき若い男と話し込んでいる。構わず中に入る。何気なく、正面の棚をみあげる。
『生きて、語り伝える』
という文字が目に飛び込む。その場で釘付けになる。
G=ガルシア=マルケス。
どきりとした。
あれは今回の仕事がヤマ場を迎えつつある最中だった。仕事関連の、お互いを追い立て合うような味気のないメール群の中に、それは紛れ込んでいた。
“マルケスって死ぬんだ”。
突然、鼓動が早まる。詩人なら、<ハトの群れの中で極楽鳥とでくわしたようだ>と書くところだろうか?
いやーー。差し出し人はーーその名まえは、それだけで脅威だ。その名は、19才から21才にかけての自分の、愚かしさの記憶を、確実に引き起こす。
もう、15年もむかしのことなのに。あやうく仕事が手につかなくなりそうだった。
しかし自分はもう、19才や21才の小僧ではない。
“マルケスって死ぬんだ”。
たった1行、いや、1文きりの思わせぶりな、しかし、差し出し人の性格あるいは気質を思えば、おそらく何の深い考えもなく、そう、単に そう思ったからそう書いただけであろうメールに、いちいち掻き乱されるような年齢ではないのだ自分は――とぐっと堪え、目前の仕事に没頭しようとする。
……事実、没頭した。極彩色の動揺がちらつくのを振り払うのに成功した、はずだった。
*
あの日の夜、夕刊の文化面には確かに、ガルシア=マルケスの死亡記事が出ている。夕食ーーというよりは既に午前0時が近いので夜食といったほうがいい腹ごしらえをしたあと、お茶を受け取るついでに、ガボの顔写真がでかでかと載ったその記事を無言で示す。コンタクトレンズを外して裸眼になっていた妻が目を細める。
ーーへえ、ノーベル賞。
すごいのね。死んだの?
・・・87才?
おかしくはないわね。
あの女とは全く異なる反応だ。
ーーガルシア=マルケス?
あなた好きだっけ?
こちらが無反応でも、妻は特に気にしない。
ーーお風呂からあがったら、栓抜くのを忘れないでよ。じゃあ、先、寝てるからね。
妻があくびをしながら寝室にひきあげたあとも、しばらくの間“87才で死んだノーベル文学賞作家”の記事を見つめ続けた。
“マルケスって死ぬんだ。”
返信はしなかった。しようがなかった。したところでおそらく、と思う。あの女のことだ。それきり、返信の返信は二度と戻ってこなかった可能性が高い。もしかして、幻だったのかと悶々とさせられたかもしれない。それならば、そうなるぐらいなら、こちらの方から相手にしてやらなかった、という状態を保った方がいい。
*
自分が無意識にそんなふうな計算を働かせていた、と自覚するのはみじめといえばみじめだ。まるで、未だに、あの女のことを、かのじょのことを、どこかで引きずっていると認めるようなものではないか。
19才や21才の小僧とは違う。もう、34才になる。
4月17日に逝去したノーベル賞作家を追悼するコーナーは、あちこちの本屋ーー自宅付近や仕事場の近くの大型書店でもーーで見かけた。
ただ、何故だか、そういうところでは買う気になれなかった。
今、気づく。ガルシア=マルケスの本を買うには、こんな本屋が相応しいのではないか。長い時間をかけて〈SUNNY BOY BOOKS〉内のすべての書棚を見まわしたあと、ようやく『生きて、語り伝える』を棚から抜き取る。そして必要以上に気のない調子を装い、レジに持っていく(でも一体、誰の目を気にしてるのやら)。
店員の若い男性に、ポイントカードをつくりますかと問われ、断る。一瞬<いい品揃えですね>と言いたくなったが、余計なお世話だろうからよしておく。多分傍から見れば、ひどく素気ない調子で店を出る。
*
生まれて初めてガルシア=マルケスを読んだのは19才になる年の、やっぱりこんな季節だった。白状すると、それを推理小説と勘違いして笑われたのがきっかけだ。
『予告された殺人の記録』
カバーをとっぱらった状態で、かのじょはその本を読んでいた。
数週間前まで高校生だった男子には少々まばゆすぎるスラリとした長い足を子どものようにばたつかせて、<推理小説?ーーまあ、そういう要素もなくはないわ>と蠱惑的に笑ってみせる。
たった一晩で、それを読んだ。それまでの自分からは想像もできないことだった。そして。この日を境に世界が変わった、と無邪気な興奮に浸った。『予告された殺人の記録』を読みおえた朝方、白々と明るむ空に目をしょぼつかせながら。
ーー世界は言葉でできている。
ガルシア=マルケスのコトバはそれを強く感じさせた。
かのじょにそう伝えると、
ーーーあたりまえじゃないの。
と、意地わるそうにしてはいるものの、実のところ、嬉しくてたまらないのを必死でこらえているような、そう、とても可愛らしい笑顔で思い切りこづかれたのだった。
*
かのじょほどには、マルケスやラテンアメリカ文学ーもっといえば詩や小説そのもの――に入れこんだわけではない。けれども、あの時期は、『百年の孤独』を、『エレンディラ』を、『幸せな無名時代』を、『戒厳令下チリ潜入記』を・・・夢中で読んだ。
マルケスのコトバは、
<ぼくに読書の喜びを教えた>。
<読書によって世界の広さを感じさせた>。
かのじょが笑う。
ーーあたりまえじゃないの。
かのじょとマルケスが、
<ぼくの19才から21才の主人公だ>。
*
「何を記憶し、どのように語るか。それこそが人生だー」。
その一節を、かのじょは事あるごとに繰り返した。
そう、まるで自分自身にそのことを言い聞かせるように。
かのじょはいつも何か書いていた。書きたがっていた。
かのじょの分身のような、かのじょとそっくりの容貌、生いたち、性格の人物を女主人公にしたてて、いろいろ書いていた。小説のような詩のような、何かをいつも。そして、自分が書いたものの、ことごとくを一度たりともかのじょは気に入ることがなかった。
だからこそ、ある日突然、無能の恋人に言った。
ーーあなたが書けばいいのに。
かのじょの恋人は耳を疑った。
ーーおれが? 無理だよ。そんなこと、想像したこともない。
かのじょは自分の申し出にうろたえる恋人をじっと見つめて繰り返す。
ーーあなたが、あたしについて書けばいいのに。あたしの夢は、詩人の恋人なのよ。
若い恋人同士の仲は、あっさりと軋みはじめる。
詩人になる努力をしない恋人にかのじょは呆れた。
かのじょの恋人は努力をしなかったのではなく、単に詩を書く才能がないだけだったのだが
ーーいや、認めろ。事実はこうだ。
“詩のために死ぬ覚悟”ができない男では、かのじょの心を繋ぎとめることができなかったのだ。
*
今朝、目を覚ましたときにはこんな休日を過ごすとは想像もしなかった。『生きて、語り伝える』を、半日も費やして読むとは思わなかった。早く帰らなければ。もうすぐ妻も帰ってくる。喫茶店の片隅で、その前に、あと少し、と思うー。青年期を振り返りながらガボはこう書く。
「全国各地からやってきた私たち田舎者にとって、ボゴタというのは国の首都であって、政府の所在地であったが、なによりもまず、詩人たちが住んでいる都だった。私たちは詩を信じていて、詩のために死ぬ覚悟ができていただけでなく、ルイス・カルドーサ・イ・アラゴンが書いたように、<詩こそが、人間が存在することの唯一の具体的な証拠である>と確信していたのである。」
2014年5月1日。
東京、15年目の春。
この町で何人の詩人と出会っただろう?
いや、この町に
詩人はどれだけいるのだろう?
34才 男性 デザイナー 既婚・子なし
居住地:世田谷・上馬
本:G=ガルシア=マルケス(旦敬介 訳)『生きて、語り伝える』(新潮社)
引用:「何を記憶し、どのように語るか。それこそが人生だー。」
_記憶の波 (小島ケイタニーラブ)
記憶の中はいつだって ちっぽけで
言葉はいつも足らなくて 溢れてる
それはまるで 波のようで
それはまるで 海のようだ
君が読めない 漢字が知りたい
それだけがほしかった
記憶の鍵はいつだって ちっぽけで
光の波にさらわれて 消えていく
君が知らない 言葉を知りたい
それだけでいい
君が知りたい すべてを知りたい
それだけがほしかった
【店主の一言メモ】
一冊の本との出会いをきっかけに、自分の愚かしい記憶を思い出し語りだす主人公は、
本に励まされながらゆっくりと過去を受け入れていきます。
波のように、風のように、行ったり来たりを繰り返しながら。
こんな風に、本はそばにいるのだと思います。
ムービー撮影:朝岡英輔